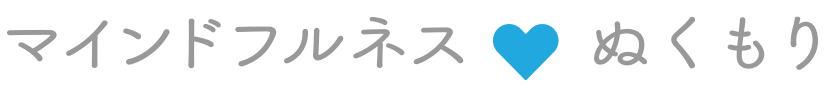マインドフルネス・セラピーとは
マインドフルネス・セラピーとは、いま起きていることに注意を向けて気づくこと。
現在、世界の多くの国において〈ストレス低減法〉として広まっています。
1980年頃、マインドフルネスを基にした「ハコミセラピー」がアメリカのロン・クルツ博士によって確立され、東洋思想が心理学の分野に取り入れられました。それは画期的なことで、多くの方に受け入れられるようになりました。「自己の内面に向き合って、本来の自分を知ること」が生きるうえでとても大切なことを教えてくれています。
マインドフルネス・セラピーは、このハコミセラピーがベースとなっています。
現在、世界の多くの国において〈ストレス低減法〉として広まっています。
1980年頃、マインドフルネスを基にした「ハコミセラピー」がアメリカのロン・クルツ博士によって確立され、東洋思想が心理学の分野に取り入れられました。それは画期的なことで、多くの方に受け入れられるようになりました。「自己の内面に向き合って、本来の自分を知ること」が生きるうえでとても大切なことを教えてくれています。
マインドフルネス・セラピーは、このハコミセラピーがベースとなっています。
マインドフルネス・セラピーの特徴
- 1
- 自分を苦しめていた囚われから解放される
- マインドフルネス・セラピーは、身体の感覚をとおして無意識とつながるので、他人からの言葉や一般的な常識や知識によって、がんじがらめになった心を解放します。

- 2
- 自分の新しい可能性が開かれてくる
- わたしたちは、自分らしく生きたいという願いを持っています。本来の自分が取り戻されてくると、自分の可能性が発揮されてきます。

- 3
- 自己肯定感が高まってくる
- 自分の存在を無条件で認められる体験が増えると、自分に自信が生まれてきます。

マインドフルネス・セラピー
愛着の絆(親子の絆)について
幼い時、常に恐怖や怒りなどを感じていると、脳はその環境で生き抜いていけるように、恐怖や怒りを感じないようになっていきます(感覚ブロック)。この状態のままでは、安心感や信頼感、人とのつながりや一体感、愛や共感が育ちにくくなってしまいます。これは、幼い自分が生きるために身につけた一時的な生きる術です。
例えば無意識の中に、自分は邪魔な存在だから、目立ってはいけない、自分は嫌われているから、みんなのように幸せになってはいけない等々の思い込みができていると、信頼して人と繋がっていくことが難しくなります。常に孤独感や無力感が出てきて自分を否定し、生きることが辛くなってしまいます。
本来人間は、自分の気持ちを分かってもらい、困った時には共に助け合い、協力し合い、苦楽を共にしたいと思っているのです。この本来の願いを叶えるためには、マインドフルネスになって無意識と繋がり、心の奥深くに沈んでいる自分を否定する「思い込み」や「信じ込み」を腑に落ちた感覚として、手放していく必要があります。それには、子供の頃に十分得られなかった体験(温かい眼差し、やさしい微笑み、穏やかな声のトーン、肌の温もりなど、安心して大丈夫、ひとりぼっちじゃない、といった愛着の絆)を、もう一度体験していくことです。
・安定した愛着の絆を体験したことがないと自分がいけないと、すべてのことで自分を責める。
・怖い、さみしい、激しい怒りなどの感情を持っている。
・誰も自分を守ってくれない、助けてくれないと思っている。
・人の目が気になり、世間体を必要以上に気にする。
・極度に失敗を恐れ、一度学んだパターンに固執する
・感覚をブロックし、ネガティブな感情を感じないようにして生きている。
・愛着の絆を体験していると
・自己信頼感、自己尊重感、安心感を持っている。
・物事を、全体性を持って肯定的に受け止められる。
・人との関係は共感的、調和的、応答的、協同的である。
・好奇心や探究心が旺盛である。
自信を持って生きるには、
愛着の絆を取り戻し、大切な存在として大事にされる体験。弱さがあっても、できないところがあっても、丸ごとの自分を認めてもらう体験が必要です。
頭の理解と身体の共感力
現代人は、常に頭から否定が出てくるので自分に自信を持って生きるのが難しいのです。ストレスに左右されない自分軸を築くために、頭と身体の特徴の違いを体験して頂きたいのです。これは体験しないとわかりません。
頭の特徴
・固定観念や概念で判断する。
・表面的。合理的、二者択一的、結果重視。
・他人の目がきになり、左右される。他人のせいにする。
・理詰めで相手を追い詰める。
・人をコントロールしようとする。
身体の特徴
・自分の存在に自信を持って居るので、ありのままの自分で居られる。
・身体は共感的、肯定的。自分の最大の理解者
・自分の弱さを隠さないので、人と深く繋がれる。
・自分を大事にしているので、他の人のことも親身になれる。
・好奇心に満ち、自由な発想ができる。
個人セッションや電話セッション、ワークショップを通して頭と身体の違いを体験すると、その真逆な反応に驚かれることでしょう。頭で否定している自分を、身体は掛け替えのない存在として大事に思っているのです。
何が起きても動揺しない、腹の据わった自分になる道を目指し、新しい試みに挑戦してみましょう。
例えば無意識の中に、自分は邪魔な存在だから、目立ってはいけない、自分は嫌われているから、みんなのように幸せになってはいけない等々の思い込みができていると、信頼して人と繋がっていくことが難しくなります。常に孤独感や無力感が出てきて自分を否定し、生きることが辛くなってしまいます。
本来人間は、自分の気持ちを分かってもらい、困った時には共に助け合い、協力し合い、苦楽を共にしたいと思っているのです。この本来の願いを叶えるためには、マインドフルネスになって無意識と繋がり、心の奥深くに沈んでいる自分を否定する「思い込み」や「信じ込み」を腑に落ちた感覚として、手放していく必要があります。それには、子供の頃に十分得られなかった体験(温かい眼差し、やさしい微笑み、穏やかな声のトーン、肌の温もりなど、安心して大丈夫、ひとりぼっちじゃない、といった愛着の絆)を、もう一度体験していくことです。
・安定した愛着の絆を体験したことがないと自分がいけないと、すべてのことで自分を責める。
・怖い、さみしい、激しい怒りなどの感情を持っている。
・誰も自分を守ってくれない、助けてくれないと思っている。
・人の目が気になり、世間体を必要以上に気にする。
・極度に失敗を恐れ、一度学んだパターンに固執する
・感覚をブロックし、ネガティブな感情を感じないようにして生きている。
・愛着の絆を体験していると
・自己信頼感、自己尊重感、安心感を持っている。
・物事を、全体性を持って肯定的に受け止められる。
・人との関係は共感的、調和的、応答的、協同的である。
・好奇心や探究心が旺盛である。
自信を持って生きるには、
愛着の絆を取り戻し、大切な存在として大事にされる体験。弱さがあっても、できないところがあっても、丸ごとの自分を認めてもらう体験が必要です。
頭の理解と身体の共感力
現代人は、常に頭から否定が出てくるので自分に自信を持って生きるのが難しいのです。ストレスに左右されない自分軸を築くために、頭と身体の特徴の違いを体験して頂きたいのです。これは体験しないとわかりません。
頭の特徴
・固定観念や概念で判断する。
・表面的。合理的、二者択一的、結果重視。
・他人の目がきになり、左右される。他人のせいにする。
・理詰めで相手を追い詰める。
・人をコントロールしようとする。
身体の特徴
・自分の存在に自信を持って居るので、ありのままの自分で居られる。
・身体は共感的、肯定的。自分の最大の理解者
・自分の弱さを隠さないので、人と深く繋がれる。
・自分を大事にしているので、他の人のことも親身になれる。
・好奇心に満ち、自由な発想ができる。
個人セッションや電話セッション、ワークショップを通して頭と身体の違いを体験すると、その真逆な反応に驚かれることでしょう。頭で否定している自分を、身体は掛け替えのない存在として大事に思っているのです。
何が起きても動揺しない、腹の据わった自分になる道を目指し、新しい試みに挑戦してみましょう。

私たちの無意識の中には根源的な力が宿っている
マインドフルネスになって、頭を休め身体で感じていくと、身体の深いところに生命力が宿っていることに気づくことができるでしょう。それは無意識の中にあって、私たちを自分らしく導いてくれる重要な働きを担っています。この根源にある、意識を超えた存在そのもの働きを「いのち」とよんでいます。
いのちの働き
「いのち」は、自分で生きようとする逞しい力を持っている。量り知れない智慧を持っている。すべての生きものの「いのち」とつながっている。進もうとするはっきりした方向性をもっている。その人に合った道を拓いてくれる等々。
「いのち」が求めているもの
私たちは、何かが満たされないときに不快感が生まれてきます。そのようなとき、「いのち」は何かを訴えているのです。「いのち」は次のような願いを持っています。
生まれながらに備わっている感覚(種子)
その人がその人らしくなるものが宿っている。
受身としての願い(発芽)
植物が発芽するには、水や太陽や土が必要です。人間においてのそれは何でしょうか。それは肌の柔らかさや温かさ、優しい声、生まれて来たことを喜んでくれる穏やかな雰囲気、しっかりと受け止められている身体の安定感等々の受け身の強い要求があります。
能動としての願い(双葉)
「いのち」の芽と根が伸び始めると、内側から湧き上がってくるものがあります。
もっと温もりが欲しい、存在にちゃんと気づいて欲しい、関心を持って話しかけて欲しい。安心したい、目と目を合わせて微笑み合いたい、等々。
本来の自分の感覚が育つ(本葉)
自由に感じたままに動く、自分で決めて自分で試みようとする、好奇心や冒険心が芽生えてくる、好きなことは好き、嫌いは嫌いと感じて行動する。こうやって人との関係性に気づき感情が育ち、感覚が育ち、自我が育っていくのです。人は、人と関わり、ふれあいを通して喜怒哀楽がはっきり感じられ「自分らしさ」が確立され、本来の自分へと成長していくのです。
自我から自己へ
自分の存在が尊重され、自信が感じられてくると、いかなる困難に遭遇しても、自分の感覚を信じ、くじけることなく、たくましく生きていくことができるのです。それは樹木に例えるなら、一本の木から森になっていくプロセスのようなものです。さらに「いのち」は常に、吸う息と吐く息のように、真逆のものが互いに関連してダイナミックな営みとなって成長していくのです。その時「いのち」は互いの存在を認め合い、尊重しあい、対等な関係として、お互いを慈しむことができるのです。
森は本来、その中に「生きとし生きるもの」が共に気持ちよく生存していける健やかな循環に満ちているものだと思います。人間も森の構成員の一人として、静かに無意識に宿っている「いのち」の声に耳を傾けていくなら、誕生→成長→成熟→死、という大きな循環があることを、自然な営みとして感じられてくることでしょう。こうして私たちの「いのち」の壮大なドラマは、太古の昔から現代にいたるまで途切れることなく、連綿と続いているのです。
そして一つの生命体として生まれてきた私たちは、身体の奥に宿っている「いのち」の可能性を存分に活かして、生きていきたいと願っているのです。この願いが満たされないままで終わりたくはないのです。セッションを受けた方々は一様に、『死にたいほど辛かったけど、本当は生きていきたい!』『このままじゃ嫌だ!』『本当は自分らしく生きていきたい!』と力強く言います。私たちは見せかけでない本物の幸せを、身を以て味わいたいから生まれ、どんなに辛くて苦しくても、こうして生きているのでしょう。
マインドフルネスになって、身体の奥の声に耳を傾けてみませんか?
いのちの働き
「いのち」は、自分で生きようとする逞しい力を持っている。量り知れない智慧を持っている。すべての生きものの「いのち」とつながっている。進もうとするはっきりした方向性をもっている。その人に合った道を拓いてくれる等々。
「いのち」が求めているもの
私たちは、何かが満たされないときに不快感が生まれてきます。そのようなとき、「いのち」は何かを訴えているのです。「いのち」は次のような願いを持っています。
生まれながらに備わっている感覚(種子)
その人がその人らしくなるものが宿っている。
受身としての願い(発芽)
植物が発芽するには、水や太陽や土が必要です。人間においてのそれは何でしょうか。それは肌の柔らかさや温かさ、優しい声、生まれて来たことを喜んでくれる穏やかな雰囲気、しっかりと受け止められている身体の安定感等々の受け身の強い要求があります。
能動としての願い(双葉)
「いのち」の芽と根が伸び始めると、内側から湧き上がってくるものがあります。
もっと温もりが欲しい、存在にちゃんと気づいて欲しい、関心を持って話しかけて欲しい。安心したい、目と目を合わせて微笑み合いたい、等々。
本来の自分の感覚が育つ(本葉)
自由に感じたままに動く、自分で決めて自分で試みようとする、好奇心や冒険心が芽生えてくる、好きなことは好き、嫌いは嫌いと感じて行動する。こうやって人との関係性に気づき感情が育ち、感覚が育ち、自我が育っていくのです。人は、人と関わり、ふれあいを通して喜怒哀楽がはっきり感じられ「自分らしさ」が確立され、本来の自分へと成長していくのです。
自我から自己へ
自分の存在が尊重され、自信が感じられてくると、いかなる困難に遭遇しても、自分の感覚を信じ、くじけることなく、たくましく生きていくことができるのです。それは樹木に例えるなら、一本の木から森になっていくプロセスのようなものです。さらに「いのち」は常に、吸う息と吐く息のように、真逆のものが互いに関連してダイナミックな営みとなって成長していくのです。その時「いのち」は互いの存在を認め合い、尊重しあい、対等な関係として、お互いを慈しむことができるのです。
森は本来、その中に「生きとし生きるもの」が共に気持ちよく生存していける健やかな循環に満ちているものだと思います。人間も森の構成員の一人として、静かに無意識に宿っている「いのち」の声に耳を傾けていくなら、誕生→成長→成熟→死、という大きな循環があることを、自然な営みとして感じられてくることでしょう。こうして私たちの「いのち」の壮大なドラマは、太古の昔から現代にいたるまで途切れることなく、連綿と続いているのです。
そして一つの生命体として生まれてきた私たちは、身体の奥に宿っている「いのち」の可能性を存分に活かして、生きていきたいと願っているのです。この願いが満たされないままで終わりたくはないのです。セッションを受けた方々は一様に、『死にたいほど辛かったけど、本当は生きていきたい!』『このままじゃ嫌だ!』『本当は自分らしく生きていきたい!』と力強く言います。私たちは見せかけでない本物の幸せを、身を以て味わいたいから生まれ、どんなに辛くて苦しくても、こうして生きているのでしょう。
マインドフルネスになって、身体の奥の声に耳を傾けてみませんか?

ストレスを生きる力に
「我慢」と「耐える」の違い
たとえば、幼い頃、親や周囲の人々から『ちゃんと我慢ができておりこうだね・・・』とか『泣かなかいで強かったね・・・』とその時に感じている辛さや悲しみを出さないで我慢した時にほめられた体験はないでしょうか。
“子供を褒めて育てる”ということを表面的な言葉だけで理解してしまうと、
子供が直感的にその時に感じている悲しさや、悔しさ、嫌さ、などの本音の気持ちを出さない方向に導いてしまいます。子供は親から叱られることほど悲しいことはありませんから、その時感じている本音を言うよりも、褒めてもらえるなら、本当の気持を言わないで我慢しようと思っても不思議はありません。
そればかりか、自分の直接的な体験ではなくても、大好きな親が理不尽な我慢をしているのを見聞きしているだけで、無意識に「どんなに理不尽でも我慢するのがいいのだ」と、自分が実際に感じていることより、感じないようにして感覚に蓋をしてしまうことがあるのです。「我慢」は自分に言い聞かせをして、感じないようにしているからできるので、これはストレスの原因になります。セッションをしていると、『これは自分の我慢ではない』と気づくことが少なくありません。
これらの「我慢」は、頭が考え出した生きる術ですが、透明な幕のようになって、自分らしく生きようとする「いのちの力」の発露を塞ぎ、本当の自分ではない自分にしてしまうのです。よく『自分が何をしたいのか、何が好きなのかわかわからない』と悩んでいる方には、心の底にこの「我慢」がこびりついていることがあります。
現代人がストレスと感じるのは、自分らしく生きられていないということです。自分の軸ができていれば自分はいま、何を感じ、何がしたいのかがわかっていますから、振り回されないで済むのです。そのために、マインドフルネスになって、本来の自分に気づくことが大切です。自分の軸に他人の価値観や「我慢」がついていては、生きにくくて当然です。ストレスを周囲の人や環境のせいにするのは簡単ですが、これではいつになっても解決しません。しかし、自分に軸を作っていくことなら、自分がやろうとさえすればできるのです。
ストレスを生きる力に変換するには
夢のような話と思われるでしょうが、一言でいえば、身体感覚を高めていくことです。お腹の声を聞き、信頼し、少しずつ行動に移していくことです。
「忍耐」という言葉があります。これは「我慢」とは違います。我慢は頭の考えで、身体の欲求を抑える方向で働きますから苦痛がたまり、周りが見えなくなり、爆発を繰り返します。しかし「忍耐」は身体が感じていることをしっかり感じ、感じたことを頭が理解して具体的な行動に移していくことです。身体が納得しているので、痛みが少ないのです。身体は感じたことがスッと理解されればそれで終わりです。喜怒哀楽がはっきりしていて、あっさりしています。感じることは、周囲の人や物事がはっきりと見えていますから、決して傍若無人な言動にはならないのです。「肚ができている」ということです。
今こそ、身体に関心を向け、その声に耳を傾け、お腹の力を養い育てていく時だと実感しています。「「忍耐」は身体の智慧が反映された状態です。
ストレスを身体感覚として感じることができるようになれば、排除したいストレスも自分の心を高め、生きる力として働いてくれるでしょう。一人では困難ですがセッションの中で、自分の存在が尊重されていると感じられてくれば、自分を苦しめていたものが、自分の最強の味方だと自然に感じられてくるでしょう。お腹の力は考える力よりもダイナミックな生命力を蓄えているのです。
現代人は頭でっかちになり過ぎて、身体の無量の力に鈍感になっていますが、今こそ、身体に関心を向け、その声に耳を傾け、お腹の力を養い育てていく時だと実感しています。
まさにいま、マインドフルネスに注目が集まっているのも、ストレスを生きる力に変えていきたいという、身体の智慧の方向性だと思っています。
たとえば、幼い頃、親や周囲の人々から『ちゃんと我慢ができておりこうだね・・・』とか『泣かなかいで強かったね・・・』とその時に感じている辛さや悲しみを出さないで我慢した時にほめられた体験はないでしょうか。
“子供を褒めて育てる”ということを表面的な言葉だけで理解してしまうと、
子供が直感的にその時に感じている悲しさや、悔しさ、嫌さ、などの本音の気持ちを出さない方向に導いてしまいます。子供は親から叱られることほど悲しいことはありませんから、その時感じている本音を言うよりも、褒めてもらえるなら、本当の気持を言わないで我慢しようと思っても不思議はありません。
そればかりか、自分の直接的な体験ではなくても、大好きな親が理不尽な我慢をしているのを見聞きしているだけで、無意識に「どんなに理不尽でも我慢するのがいいのだ」と、自分が実際に感じていることより、感じないようにして感覚に蓋をしてしまうことがあるのです。「我慢」は自分に言い聞かせをして、感じないようにしているからできるので、これはストレスの原因になります。セッションをしていると、『これは自分の我慢ではない』と気づくことが少なくありません。
これらの「我慢」は、頭が考え出した生きる術ですが、透明な幕のようになって、自分らしく生きようとする「いのちの力」の発露を塞ぎ、本当の自分ではない自分にしてしまうのです。よく『自分が何をしたいのか、何が好きなのかわかわからない』と悩んでいる方には、心の底にこの「我慢」がこびりついていることがあります。
現代人がストレスと感じるのは、自分らしく生きられていないということです。自分の軸ができていれば自分はいま、何を感じ、何がしたいのかがわかっていますから、振り回されないで済むのです。そのために、マインドフルネスになって、本来の自分に気づくことが大切です。自分の軸に他人の価値観や「我慢」がついていては、生きにくくて当然です。ストレスを周囲の人や環境のせいにするのは簡単ですが、これではいつになっても解決しません。しかし、自分に軸を作っていくことなら、自分がやろうとさえすればできるのです。
ストレスを生きる力に変換するには
夢のような話と思われるでしょうが、一言でいえば、身体感覚を高めていくことです。お腹の声を聞き、信頼し、少しずつ行動に移していくことです。
「忍耐」という言葉があります。これは「我慢」とは違います。我慢は頭の考えで、身体の欲求を抑える方向で働きますから苦痛がたまり、周りが見えなくなり、爆発を繰り返します。しかし「忍耐」は身体が感じていることをしっかり感じ、感じたことを頭が理解して具体的な行動に移していくことです。身体が納得しているので、痛みが少ないのです。身体は感じたことがスッと理解されればそれで終わりです。喜怒哀楽がはっきりしていて、あっさりしています。感じることは、周囲の人や物事がはっきりと見えていますから、決して傍若無人な言動にはならないのです。「肚ができている」ということです。
今こそ、身体に関心を向け、その声に耳を傾け、お腹の力を養い育てていく時だと実感しています。「「忍耐」は身体の智慧が反映された状態です。
ストレスを身体感覚として感じることができるようになれば、排除したいストレスも自分の心を高め、生きる力として働いてくれるでしょう。一人では困難ですがセッションの中で、自分の存在が尊重されていると感じられてくれば、自分を苦しめていたものが、自分の最強の味方だと自然に感じられてくるでしょう。お腹の力は考える力よりもダイナミックな生命力を蓄えているのです。
現代人は頭でっかちになり過ぎて、身体の無量の力に鈍感になっていますが、今こそ、身体に関心を向け、その声に耳を傾け、お腹の力を養い育てていく時だと実感しています。
まさにいま、マインドフルネスに注目が集まっているのも、ストレスを生きる力に変えていきたいという、身体の智慧の方向性だと思っています。

心の自由(自分らしく生きるには)
心の自由は感覚です。現代は頭があまりにも支配的になっているので、身体の感覚が感じられないのが実情です。
まずは、身体に手を当てる体験から
マインドフルネスになって、気持ちが落ち着いてから、首に両手を当てたり、ペアになって肩や背中に手を当てたりしてみます。どんな感じがするでしょうか。はじめは何にも感じられないかもしれません。それでいいのです。感じたふりをしたり、相手が喜びそうなことを言わないでいいのです。触れられるのが苦手だと感じたのなら、正直にそう言っていいのです。感じ方に正解も間違いもないのですから、たったそれだけでも、身体はホッとするかもしれません。私たちは常に正解でなければいけないと、思い込んで来ました。
身体の感覚は知識や常識にしばられていない
身体は今の事しか感じていないし、本人にしか解らないのです。他の人がその人の感覚をそっくりわかることはできませんが、共感することはできます。『今そう感じているのね。わかったわ』と、一旦、自分以外の人に自分が感じていることを共感してもらう体験は、「自分が存在していていい」という安心感に繋がっています。自己肯定感がもてないのは、何かができないからではなく、単純に自分の気持ちに共感してもらった体験が少ないのです。
心を自由に解き放していくには
私は2013年に野口整体金井流の金井蒼天先生に出会い、目から鱗が落ちる想いがしました。野口晴哉氏の整体理論は、体の歪みは、生理的なものだけでなく、心理にも影響をもたらす。体は意識しない運動で体を調整していく力がある。自分の体の中には健康になろう、幸せになろうとする働きがあることを、教えています。心が苦しいからと、心のことだけやっていては偏ってしまう。心身の偏りを調整していくことが大事だと知りました。それ以来、心と身体の両面からのアプローチとして「活元運動」を取り入れています。
まずは、身体に手を当てる体験から
マインドフルネスになって、気持ちが落ち着いてから、首に両手を当てたり、ペアになって肩や背中に手を当てたりしてみます。どんな感じがするでしょうか。はじめは何にも感じられないかもしれません。それでいいのです。感じたふりをしたり、相手が喜びそうなことを言わないでいいのです。触れられるのが苦手だと感じたのなら、正直にそう言っていいのです。感じ方に正解も間違いもないのですから、たったそれだけでも、身体はホッとするかもしれません。私たちは常に正解でなければいけないと、思い込んで来ました。
身体の感覚は知識や常識にしばられていない
身体は今の事しか感じていないし、本人にしか解らないのです。他の人がその人の感覚をそっくりわかることはできませんが、共感することはできます。『今そう感じているのね。わかったわ』と、一旦、自分以外の人に自分が感じていることを共感してもらう体験は、「自分が存在していていい」という安心感に繋がっています。自己肯定感がもてないのは、何かができないからではなく、単純に自分の気持ちに共感してもらった体験が少ないのです。
心を自由に解き放していくには
私は2013年に野口整体金井流の金井蒼天先生に出会い、目から鱗が落ちる想いがしました。野口晴哉氏の整体理論は、体の歪みは、生理的なものだけでなく、心理にも影響をもたらす。体は意識しない運動で体を調整していく力がある。自分の体の中には健康になろう、幸せになろうとする働きがあることを、教えています。心が苦しいからと、心のことだけやっていては偏ってしまう。心身の偏りを調整していくことが大事だと知りました。それ以来、心と身体の両面からのアプローチとして「活元運動」を取り入れています。